国民年金
ねんきんネット
「ねんきんネット」とは、年金加入者や受給者の方が、ご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
公的年金の意義
国民年金、厚生年金などの公的年金は、やがて訪れる長い老後生活の基本部分を生涯にわたって保障します。少子高齢化が進展する社会において、老後生活の基本部分が公的年金によって確保されることは、高齢者の安心のみならず、親の経済的な心配をしながら生活しなくて済む子どもたちの安心にもつながります。
国民年金制度やメリットなどは動画でも視聴できます。
20歳になったら国民年金 「国民年金制度の内容やメリット編」 4分15秒(YouTube厚生労働省チャンネル)(外部リンク)
公的年金について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
公的年金の仕組み
法律に従って国が管理・運営する公的年金制度は、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人全員〔性別、国籍を問いません〕が加入する国民年金(基礎年金)と、その上乗せとなる国民年金基金、厚生年金によって2階建ての構造をしています。
- 第1号被保険者 → 20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など
- 第2号被保険者 → 会社員・公務員など
- 第3号被保険者 → 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
基礎年金の部分は全員共通ですが、それぞれの職業や雇用形態に応じて第1号から第3号に分類され、保険料の支払い方法や、受け取る年金が異なります。
年金加入、資格切替えの手続きについて
| こんな時 | 届出先 | 必要なものなど |
|---|---|---|
| 20歳になった時(厚生年金の加入者、加入者に扶養される配偶者は除きます) | 手続き不要 | |
| 厚生年金に加入する時 | 勤務先 | 本人(配偶者)の基礎年金番号のわかるもの |
| 厚生年金に加入していた方が退職した時(扶養していた配偶者がいる時は一緒に届出をしてください) | 住所地の市町村役場 | 退職日が確認できる書類、本人(配偶者)のマイナンバーの分かるもの又は、基礎年金番号のわかるもの |
| 配偶者の扶養から抜けた時(収入が増えたり、離婚したとき) | 住所地の市町村役場 | 扶養から外れた日が確認できる書類、本人のマイナンバーの分かるもの又は、基礎年金番号のわかるもの |
国民年金の保険料
国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーター、学生)の方の月々の保険料は16,980円(令和6年度)です。国民年金の保険料はまとめて前払い(前納)すると割引となり、口座振替で前納すると、さらに保険料が安くなります。
| 基本額 | 割引額 | 納付額 | |
|---|---|---|---|
| 納付書での納付 | 17,510円 | 0円 | 17,510円 |
| 6か月前納 | 105,060円 | 850円 | 104,210円 |
| 1年前納 | 210,120円 | 3,730円 | 206,390円 |
| 2年前納 | 425,160円 | 15,670円 | 409,490円 |
| 基本額 | 割引額 | 納付額 | |
|---|---|---|---|
| 翌月末振替 | 17,510円 | 0円 |
17,510円 |
| 早割(当月末振替) | 17,450円 | 60円 | 17,450円 |
| 6か月前納 | 105,060円 | 1,190円 | 103,870円 |
| 1年前納 | 210,120円 | 4,400円 | 205,720円 |
| 2年前納 | 425,160円 | 17,010円 | 408,150円 |
(注意)令和7年度の1か月当たりの保険料は、17,510円です。
国民年金保険料の納め方
| 現金納付 | 納付書に現金を添えて納めます。全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納められます。 | 納付書は、年金事務所に連絡をして、お取り寄せください。 また、「2年納付」で納付するためには、お手続きが必要です。 役場・年金事務所にお問い合わせください。 |
|---|---|---|
| 電子納付 | インターネットや携帯電話を使って納めます。事前に金融機関との契約が必要ですが、納める時に窓口へ足を運ぶ必要がなくなります。 | 電子納付の契約方法については、各金融機関へお問い合わせください。 |
| 口座振替・クレジットカード納付 | 一度手続きをすれば、指定の口座およびクレジットカードから、毎月自動的に保険料が引き落とされます。手間も省け、納め忘れもありません。また、口座振替には、毎月の保険料が割引になる『毎月早割』制度もあります。 | 口座振替およびクレジットカード納付の手続きは、役場・年金事務所、口座振替は引き落としを希望する口座のある郵便局、銀行等の金融機関でもお手続できます。 |
国民年金保険料の納付方法などは動画でも視聴できます。
20歳になったら国民年金「保険料の納付方法編」 6分55秒(YouTube厚生労働省チャンネル)(外部リンク)
保険料を納めることが難しい時は?
国民年金は20歳から60歳までの全ての人が加入し、保険料を40年納めます。しかし、長い人生のうちには、所得が少なかったり、失業といった経済的な事情から保険料を納めるのが困難な時期もあるかもしれません。そんな時、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。
免除・納付猶予制度は動画でも視聴できます。
20歳になったら国民年金「免除・納付猶予編」5分17秒(YouTube厚生労働省チャンネル)(外部リンク)
法定免除申請
本人が生活保護による生活扶助を受けている場合や、障害年金(2級以上)を受けている場合に保険料が免除となります。
産前産後期間の免除申請
平成31年2月1日以降に本人が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の保険料が免除となります。
免除(全額・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定基準以下の時、それぞれの所得状況に応じて、保険料の全額、または一部の支払が免除となります。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の時、保険料の後払いが認められます。所得の基準は、『全額免除』の目安を参考にしてください。
学生納付特例申請
学生の方で、本人の所得が一定額以下の時、保険料の後払いが認められます。
学生納付特例制度は動画でも視聴できます。
20歳になったら国民年金「学生納付特例編」5分25秒(YouTube厚生労働省チャンネル)(外部リンク)
| 制度 | 申請期間 | 承認期間 | 免除審査基準対象者 | 単身者の所得基準額 |
|---|---|---|---|---|
| 法定免除 | 免除基準該当時 | 免除基準該当期間 | 本人 | — |
| 産前産後期間の免除 | 出産予定日の6か月前から可能 | 出産(予定)日の属する月の前月から4か月 (注意)多胎の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月 |
本人 | — |
| 全額免除 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 7月から翌年6月 | 本人、配偶者、世帯主 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 4分の3免除 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 7月から翌年6月 | 本人、配偶者、世帯主 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 7月から翌年6月 | 本人、配偶者、世帯主 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 7月から翌年6月 | 本人、配偶者、世帯主 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 納付猶予 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 7月から翌年6月 | 本人、配偶者 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
| 学生納付特例 | 原則2年1か月前まで遡ることが可能 | 4月から翌年3月 | 本人 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
『免除/納付猶予/学生納付特例』の承認期間と「未納」期間の違い
| 全額免除 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | 若年者納付猶予 | 学生納付特例 | 未納 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受給資格期間に入ります。(注釈) | 受給資格期間に入ります。(注釈) | 受給資格期間に入ります。(注釈) | 受給資格期間に入ります。(注釈) | 受給資格期間に入ります。(注釈) | 受給資格期間に入ります。(注釈) | 資格に入りません |
| 全額免除 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | 若年者納付猶予 | 学生納付特例 | 未納 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2の年金(平成21年3月までは1/3) | 5/8の年金(平成21年3月までは1/2) | 6/8の年金(平成21年3月までは2/3) | 7/8の年金(平成21年3月までは5/6) | 算入されません | 算入されません | 算入されません |
| 全額免除 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | 若年者納付猶予 | 学生納付特例 | 未納 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 保険料を納めた期間として扱われます。万一この期間中に事故や病気になっても、障害や遺族基礎年金の額が安くなることはありません。 | 資格に入りません |
(注釈)「年金をもらうには、25年以上かけないとだめ」と聞いたことがないでしょうか?正確に言うと『老齢基礎年金の受給には、25年以上の受給資格期間が必要』なのですが、免除や納付猶予が承認された期間は、この『受給資格期間』として年数計算ができます。また、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。
例
- 厚生年金 3年 + 国民年金 2年 + 他は全て未納 = 受給資格期間 5年 → 年金をもらえない
- 厚生年金 15年 + 国民年金 5年 + 免除承認5年 = 受給資格期間 25年 → 年金をもらえる
- 厚生年金 5年 + 国民年金 5年 + 他は全て未納 = 受給資格期間 10年 → 年金をもらえる
国民年金からの給付(老齢/障害/遺族)
国民年金には、みなさんの生活の基本部分を保障する3つの基礎年金があります。
老齢基礎年金
保険料を納めた方が、65歳から生涯に渡って受けることができる年金です。 老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間保険料を納めて、満額となる「831,696円(令和7年度)」を受け取ることができます。保険料を納めた期間が40年に満たない人は、不足期間に応じて年金が減額されていきます。ただし、受給資格期間が10年に満たないと、老齢基礎年金を受けることができません。
障害基礎年金
国民年金加入中(もしくは、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間中)に初診日があるケガや病気によって障害が残ってしまった時、障害の程度に応じて受けることができます。 ただし、障害基礎年金は、単に障害が残ってしまったというだけではなく
- 20歳から初診日の前々月までの期間のうち、保険料の未納期間が1/3未満である
- 初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がまったく無い
上記2つの保険料納付要件のうち、いずれかをクリアしていないと、障害基礎年金を請求することができません。
年金額 1級1,036,625円/2級829,300円(令和7年度)
(注意)障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合には20歳未満)の子がいる場合には加算がつきます。
遺族基礎年金
国民年金に加入中や、老齢基礎年金を受けている又は受給資格期間を満たしている方等が亡くなった時、生計を維持されていた18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害がある場合には20歳未満)の子がいる配偶者か、その子ども本人に支払われます。 遺族基礎年金にも、障害基礎年金と同様の保険料納付要件があり
- 20歳から亡くなった月の前々月までの期間のうち、保険料の未納期間が1/3未満である
- 亡くなった月の前々月までの1年間に、保険料の未納がまったく無い
上記2つの保険料納付要件のうち、いずれかを亡くなった方がクリアしていないと、遺族基礎年金を請求することができません。
年金額 (子のある配偶者が受ける場合)
831,700円(令和7年度)+子の加算額(1,2人目239,300円、3人目以降79,800円)
国民年金の独自給付(寡婦/死亡一時金)
遺族基礎年金は18歳未満(障害がある場合には20歳未満)の子がいる妻か、子ども本人しか受給できません。そこで国民年金に加入していた方が亡くなった時、保険料の掛け捨てを少しでも解消するため、国民年金には以下2つの独自給付があります。
寡婦年金
国民年金保険料の納付済み期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時、10年以上婚姻関係のあった妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。 ただし、妻が65歳前に自身の老齢基礎年金を繰り上げて受給した時は、その時点から寡婦年金は支給停止となります。
死亡一時金
国民年金の保険料を納めた期間が合計で3年以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金を受けられる資格のある人が居ない時、遺族(生計を共にしている配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に対して、一時金として支給されます。
| 国民年金の保険料を納めた月数 | 金額 |
|---|---|
| 36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
| 180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
| 240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
| 300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
| 360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
| 420ヶ月以上 | 320,000円 |
- 申請免除によって、保険料を一部(1/4、1/2、3/4)納付した月は、それぞれ1/4ヶ月、1/2ヶ月、3/4ヶ月として保険料を納めた月数を計算します。
- 付加保険料を36月以上納めたときは、8,500円が加算されます。
国民年金の独自給付(付加年金)
国民年金保険料(17,510円)に毎月400円を上乗せして納めると、将来年金を受け取る時に、毎年、老齢基礎年金に加算される年金です。『(400円を)納付した月数×200円』が将来の年金に毎年加算されるので、支払った保険料は2年で元が取れます。年金額を大きく増やすことはできませんが(最大40年納付で年96,000円)、割安な保険料で回収率が高い、とてもお得な年金です。
(注意)付加年金保険料(400円)を納めるには、役場での手続きが必要です。
受給資格期間とは
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 昭和36年4月以降に厚生年金へ加入した期間
- 昭和61年4月以降、サラリーマンや公務員の夫・妻に扶養される配偶者として、国民年金の第3号被保険者に認定された期間
- 免除や納付猶予、学生納付特例を承認された期間
- 合算対象期間(カラ期間)
(注釈) 合算対象期間(カラ期間)
- (ア)加入してもしなくても良かった(任意加入であった)ために、国民年金へ加入しないことを選択していた期間
- (イ)昭和36年4月以降に加入していた厚生年金の脱退手当金を受け取った期間
カラ期間は、老齢基礎年金を受けるための審査には年数を算入できますが、年金額はゼロ円計算となります。
平成3年3月以前の学生、昭和61年3月以前、サラリーマンや公務員の夫または妻に扶養されていた配偶者、20歳から60歳までの間に海外在住期間がある人は、(ア)のカラ期間をお持ちになっている場合が多く、カラ期間を計算して初めて老齢基礎年金の受給権が発生する方もめずらしくありません。
年金の請求手続きはご自身で
「一定の年齢に到達した」、「障害状態になってしまった」等、年金の受給に必要な条件が揃ったとしても、年金は自動的に振り込まれてはきません。ご自身の請求手続きによって、初めて年金の受給権が発生します。 実際に年金事務所等で自分の年金記録を打ち出してもらうと、旧姓時代の年金記録や、何十年も前に短期間だけ加入した厚生年金の記録が抜け落ちている方が多くいらっしゃいます。年金の請求漏れを防ぐ観点からは、手続きを通して、ご自身がこれまでの年金記録、受給資格等を再度確認した上で年金の請求をすることは、非常に大きな意味を持ちます。 手続きに必要な書類、請求先は、今まで加入した制度や年金の記録によって一人ひとり異なりますので、請求前にご相談ください。
年金の請求先一覧表
| 今までの年金加入状況 | 請求先 |
|---|---|
| 国民年金の第1号被保険者期間のみ | 現住所地の市町村役場 |
| 厚生年金、共済年金等の第2号被保険者期間がある | 年金事務所(注釈:共済年金期間のみの方は、各共済組合です) |
| サラリーマンや公務員の夫または妻に扶養されていた第3号被保険者の期間がある | 年金事務所 |
| 今までの年金加入状況 | 請求先 |
|---|---|
| 障害の原因となるケガや病気の初診日が、第1号被保険者期間中にある | 現住所地の市町村役場 |
| 初診日が厚生年金加入期間中にある又は第3号被保険者期間中にある | 年金事務所 |
| 初診日が20歳前にある | 現住所地の市町村役場 |
| 今までの年金加入状況 | 請求先 |
|---|---|
|
現住所地の市町村役場 |
|
年金事務所 |
(注釈)「被用者年金一元化法」により、平成27年10月1日以降に年金を受け取る権利が発生する被保険者及び受給者の方については、各共済組合のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。
年金を受けている方の手続き
現状確認方法について
年金を受け取っている方が、健在であることを住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)の情報により確認していますが、住基ネットの情報で確認が取れない方は、誕生月に「年金受給権者現状届」の届出が必要です。
現況届の提出が必要となる方
- 日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
- 外国籍(外国人登録)の方
- 外国にお住まいの方
(注意)日本年金機構より送付される現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要です。
氏名の変更、住所変更、年金を受け取っている口座の変更
変更届の用紙は役場に備えてあります。氏名及び住所の変更については、手続きがなされないと年金の支払がストップしてしまうこともありますので、忘れずに手続きをお願いします。
年金を受けている方が亡くなった時
年金を受けている方が亡くなった時には、市町村役場への「死亡届」とは別に、年金の死亡手続きが必要になります。年金の死亡手続きは、亡くなった方が受けていた年金の種類によって窓口が異なります。年金証書等をお持ちになって役場までご相談の上、それぞれの窓口で手続きをお願いします。
特別障害給付金
障害基礎年金の1級、2級に該当する障害状態であるにも関わらず、国民年金に任意加入していなかったことによって、障害基礎年金等を受給できない方に対して、福祉的措置として『特別障害給付金制度』が平成17年4月より始まりました。
| 対象者 | 対象者の範囲 | |
|---|---|---|
| (1) | 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 | A又はBの昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信制は除く。)
|
| (2) | 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者 |
|
(1)、(2)のいずれかに該当し、任意加入していなかった期間内に初診日(注)がある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
(注意)…初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
- 障害基礎年金1級相当に該当する方 : 月額56,850円(令和7年度)
- 障害基礎年金2級相当に該当する方 : 月額45,480円(令和7年度)
(注意)支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(注意)ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。
(注意)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。
(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
(注意)経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の支給は停止となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970












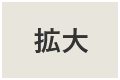



更新日:2025年04月10日