令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当が拡充されます。
主な改正内容
所得制限の撤廃
これまで、所得制限限度額を超えた方には特例給付(児童1人につき5,000円)を支給し、所得上限限度額を超えた方には児童手当・特例給付が支給されませんでしたが、令和6年10月分からはこれらの所得制限が撤廃され、保護者の所得にかかわらず児童手当が受給できるようになります(特例給付は廃止となります)。
高校生年代(18歳年度末)まで支給期間延長
これまで、支給対象となる児童は中学校修了(15歳年度末)まででしたが、令和6年10月分から、高校生年代(18歳年度末)までに延長されます。18歳年度末までの児童であれば、高校に在学していない場合も対象となります。ただし、保護者の方が監護していない場合は対象外です。
第3子以降の児童の手当額(多子加算)を増額
これまで、第3子以降の手当額は3歳から小学校修了までの児童に適用され、月額15,000円でしたが、令和6年10月分からは支給対象児童全てに適用され、月額30,000円に増額されます。
多子加算の算定対象を22歳年度末の子まで拡大
これまで、上記の多子加算の算定は高校生以下の児童から第1子と数えて第3子以降に適用されていましたが、令和6年10月分から22歳年度末の子まで算定対象が拡大されます。該当の子が学生であるか否か、またその収入の多寡にかかわらず対象となります。ただし、保護者の方が養育している場合に限ります。
(注意)この場合の養育とは、監護相当の日常的な世話・保護および生計費の相当部分の負担をさします。該当の子が独立して生計を営んでいる場合や、婚姻して配偶者に扶養されている場合など、保護者が養育しているとは言い難い場合は対象となりません。なお、該当の子と別居していても、定期的な面会や仕送り等があれば認められる場合があります。
支給回数を年6回に変更
これまで、2月、6月、10月の年3回支給していたところ、令和6年10月分(令和6年12月支給)から2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、各前月までの2か月分を支給します。
申請について
申請が必要な方
以下に該当する方は、申請が必要です。該当の方には通知を送付しますが、お子さんと別居されている場合などは通知が送付されないことがあります。その場合の申請方法は、以下「上記1または2に該当する方で、別居中のお子さん(高校生年代から22歳年度末まで)を養育されている方へ」をご確認ください。
お手続きが必要かどうかは、こちらのフローチャートからもご確認いただけます。
児童手当制度改正 手続き確認フローチャート(PDFファイル:290.8KB)
(注意)令和6年10月1日時点の状況でお考えください。
1. 児童手当または特例給付を受給していない方
- 中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 所得制限により児童手当や特例給付を受給していない方
⇒認定請求書の提出が必要です。
下記2にも該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:339.4KB)
2. 児童手当または特例給付を受給中で、18歳年度末以後(高校卒業後)から22歳年度末までのお子さんを養育している方(養育しているお子さんが3人以上の場合のみ)
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:93KB)
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:87KB)
(注意)記入にあたっては、確認書裏面の注意事項をよくご確認ください。
(注意)該当のお子さんについて、受給者となる方が養育(監護相当の日常的な世話・保護および生計費の相当部分の負担)している場合のみ対象となります。該当の子が独立して生計を営んでいる場合や、婚姻して配偶者に扶養されている場合など、受給者となる方が養育しているとは言い難い場合は対象となりません。なお、該当の子と別居していても、定期的な面会や仕送り等があれば認められる場合があります。該当のお子さんが学生であるか否か、またその収入の多寡は問いません。
(注意)審査の過程で、生計費の負担をしていることの証明となる書類の提出をお願いする場合があります。
上記1または2に該当する方で、別居中のお子さん(高校生年代から22歳年度末まで)を養育されている方へ
別居中のお子さんがいる場合(実際には同居していても、住民票上別居または別世帯となっている場合を含みます)、町がお子さんの養育状況を把握できないため、上記に該当する場合でも通知が送付されないことがあります。ご自身で上記の申請書類をダウンロードいただくか、子育て支援課までご相談ください。
(注意)別居中のお子さんがいる方は、以下の「別居監護申立書」の提出も必要になります。
申請方法
以下の期間内に、上記申請書類と下記添付書類をあわせて郵送または持参にて提出してください。提出が遅れると、支給が遅れたり、支給されない月が発生する可能性があります。
添付書類
- 申請者(父母等のうち、所得の高い方)の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードの表面 など) *郵送の場合のみ
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者の健康保険証の写し(記号・番号および保険者番号の部分にマスキングしたもの) (注意)お子さんの保険証ではありません。
通帳またはキャッシュカードの写しおよび健康保険証の写しは、児童手当または特例給付を受給中の方は不要です。
申請期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
郵送の場合は必着
提出先
郵便番号355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 子育て支援課(2階10番窓口)
その他
- 新たに認定される方の場合、原則として父母等のうち所得の高い方が受給者となります。申請は、受給者となる見込みの方がおこなってください。父母等で所得が同程度の場合や、一時的に所得の逆転が起こっている場合などは子育て支援課までご相談ください。
- 上記以外の方は原則申請不要となります。今回の制度改正により児童手当が増額、または特例給付から児童手当に変更となる方には、11月下旬ごろまでに増額改定通知書または児童手当認定通知書を送付しますので、内容をご確認ください。
- これまで支払期ごとに支払通知書を送付していましたが、令和6年10月期支払をもって廃止となります。12月期以降は、通帳記帳などによりご確認ください。支給に係る証明書が必要な方には、事前に子育て支援課までご相談いただければ児童手当支給証明書を発行します。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200












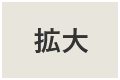



更新日:2024年09月20日